
少し前のDeSciの記事を読んだけど,よく分かりませんでした.もっと分かりやすくお願いします!
本記事は,このようなトピックにお答えします.
本記事の内容・分散型科学(DeSci)という言葉の説明
・「分散型」の考え方の説明
・ブロックチェーンの概要
・分散型科学(DeSci)の定義
・現代科学が抱える課題の整理

こんにちは.
元研究者のフールです.
派遣社員の研究員だった頃,実験室の “P2P” を “Peer to Peer” と勘違いした後輩と出会いました.
それをきっかけに仮想通貨やNFTなどの暗号資産の勉強を始め,GameFi・Move to Earn・Read to Earn などを始めとする新しい動きがたくさんあることを知りました.
2020年頃からその動きはサイエンス分野にも応用され始め,最近ではそれを分散型科学(DeSci)と呼び,業界関係者の注目を集めています.

DeSciに興味が湧いた私は,ちょっと調べて当ブログの記事として公開したのですが…やっぱり,分からない(笑).
これではDeSciが何なのか全然伝わらないですね.
冒頭の女の子の感想は正しい!
そして,その原因は明らかです.
だって,私自身がちゃんと理解していないから!

そんな状態では自分の言葉で表現はできませんよね(笑)
ただ,何となくの理解ですが,DeSciは既存の科学研究の在り方を変えると期待できる動きってことは分かっています.
その動きを理解し注目しておくことは重要だと考えたので,DeSciをちゃんと勉強することにしました.

これから何回かにわたって,DeSciについて私が調べたことをまとめていきますね!
サマリー・「分散型」は「中央集権化」の反対の意味で使われる言葉
・ブロックチェーンは「分散型」の世界を実現する技術
・DeSciは「科学(知識・技術)の民主化」運動
分散型科学(DeSci)という言葉を知る

まず分散型科学(DeSci)という言葉について勉強しましょう.
「分散型」と「科学」の2つの単語からなる言葉で,英語では “Decentralized science” と表現され,その略語が “DeSci” です.
「デサイ」「デサイス」「 デ・シー」「ディーサイ」など読み方は色々あるみたいでが…

当ブログでは「分散型科学」・DeSci・「ディーサイ」のどれかで書くようにしますね.

表記の仕方や読み方は分かりました.ただ,DeSci が何なのかは全然分かりません.

もちろんです!これで「なるほど!」と理解する人はいないでしょう(笑)

そもそも「分散型」って何ですか?

気になりますよね!次は「分散型」について少し勉強しましょう!
「分散型」という概念を理解する


「分散型」は「中央集権化」の反対の意味で使われる言葉ですね.「分散化」とか「分散性」と言ったり書く場合もありますよ!

中央集権化って何ですか?

世の中のサービス・システムの大半には組織という管理者(中央管理者)が存在します.例えば,政府・銀行・会社などが中央管理者ですね!

政府はお金を発行し,管理・送金は銀行が行い,モノ・サービスはそれぞれの会社が提供するって感じですか?

その通りです!そして,私たちはそれぞれの中央管理者を信用してお金や個人情報を預けるようになりました.これが「中央集権化(中央集権的なプロセス)」です.
Googleで検索したり,Amazonで商品を購入したり,LINEでメッセージを送ったり etc.
私たちの生活はとっても便利にりました!
でも最近になって,この信用をベースにした社会構造,つまり,中央集権化による社会問題が様々な分野で顕在化しはじめました.

それが「個人情報の集中」と「データの所有権の問題」です!
個人情報の集中と漏洩問題
Google・Facebookなどの一部の企業や特定のプラットフォーム(SNSなど)に個人情報が集中したことで,ハッキングによる情報漏洩の懸念が高まっています.
先日もLINEヤフーで利用者情報などが漏洩した問題が報告されましたね!
データの所有権の問題
オンラインを通じて提供されるコンテンツが,サービス提供者の一方的な都合であっけなく消滅しちゃうことも問題となっています.
私たちがお金を払って購入したソシャゲのアイテムや電子書籍の書籍データなどは,事業者のサービス終了とともに使えなくなるっておかしいと思いませんか?
ただ,データの管理&所有権は事業者が持っていて,私たちはその閲覧権や使用権しか持っていません.

だから,現状は仕方ないんです…
意思決定がコントロールされる
便利で豊かな日常生活を求めて,私たちは特定の事業・サービスに依存します.
すると,ユーザー数が増えて,利用者のデータも蓄積されていきますね.
そのデータ解析を行うことで利便性が向上した新サービスが展開され,私たちはさらに特定の事業・サービスに依存しちゃいます.
この繰り返しで企業は大きく成長し,やがて管理社として君臨するようになるんですね.

「私たちの意思決定が一定の範囲でコントロールされるんだよ!」と言うと過激な表現だけど,あながち間違いでもないと思います!

この状況に反対・抵抗する思想が「分散型」「分散化」なんですね!

正解!その通りです!
「分散型」の世界
「中央集権化」の問題点は管理者に情報・権利・お金が集中すること.
集中する理由は,国・企業・団体が管理するサーバーにデータを集約するから.
それなら,データをサーバーじゃなくて,世界各地に散らばっているパソコン(=ノード)に分散させて管理すれば良いのでは?
データが一か所に集まらないからハッキングの懸念も減るし,管理者(特定の人・組織)不在なのでデータを独占することもできないでしょ!

これが「分散型」の概念になります!

なるほど~って思うんだけど,データが散らばってたら何がどこにあるのか分からなくならないの?

取引を記録する共通のデジタル台帳技術(=ブロックチェーン)があるから大丈夫だよ!

ブロックチェーン?

それでは次はブロックチェーンについて簡単に学ぼう!
ブロックチェーンの基礎を知る
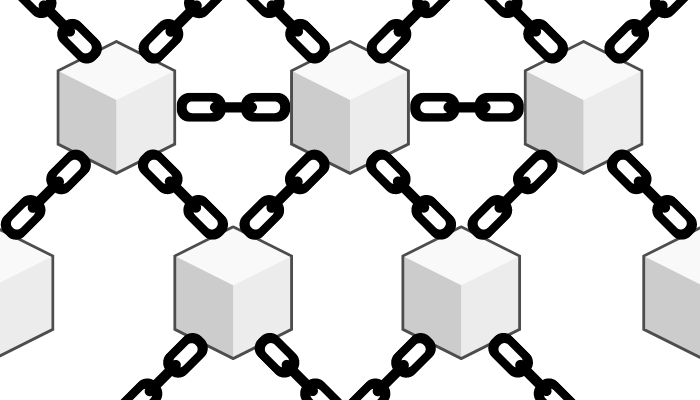
ブロックチェーンは「分散型」の世界を実現する技術で,漢字では「分散型台帳技術」と表現されています.
データの取引を行うノード(世界各地に散在するパソコン)は取引内容を記録する箱(ブロック)を取引毎に生成します.
追加されたブロックがコンピューター計算で承認されると,その時点での末尾のブロックに繋がります.

この繰り返しでブロックが鎖(チェーン)のように連なった状態をイメージすると分かりやすいですね!
ブロックを作成するノードが世界各地に散らばっているので,データが一か所に集中することはありません.
でも,その取引の詳細(ブロックの中身)は全て公開されているので,どのノードからでも確認できる(=透明性がある)し,追跡することも可能です(=トレーサビリティ).

ブロックチェーンは,透明性&トレーサビリティを備えた「分散型ネットワーク」を形成できる技術なんですね!

おっいいですね!その通り!!
そして,このブロックチェーンの特徴は,取引履歴(ブロック)の改ざんが極めて難しいってこと!
- 新規のブロックを末尾のブロックに連鎖させるシステム!
- 改ざん(すでに連なっている任意のブロックを取り出し,中身を書き換えて,戻す)にはとんでもない計算力が必要!!
改ざんするには莫大なお金と時間が要るので実行できる人は限定されるし,それを次回説明するDAOが承認するかどうかは別の問題となります.
web3(ウェブスリー)

ブロックチェーンのことを調べていると “web3” という言葉が頻出してきます.

web3?

これはインターネットの歴史を3段階に分けたときの3番目を表す用語です. “Web3” とか “Web3.0” と書かれる場合もありますが,どれも指すものは同じです.

ってことは “Web1” や “Web2” もあるんだよね?

その通りです!以下に概要をまとめますね!
Web1
インターネットが登場し,人々はパソコンを使うようになり,個人が情報を発信できるようになった時代です.
色々なものがデジタル化され,我々の生活は激変!
でも,情報伝達はまだ発信者から受信者への一方通行でした.
Web2
ブログ,SNS,YouTubeなどの登場で,これまで情報の受信者であったユーザーがコンテンツの作成&共有をできるようになった時代です.
メインツールはパソコンからスマホに変わって,情報の伝達も双方向へ.
口コミ(レビュー)などの個人の感想が重要視されるようになったことでインフルエンサーというポジションが誕生しましたね!
先に挙げた中央集権的構造が形成された時代でもあります.
web3
非中央集権化を目指す人々が「分散化」の理念の下に様々なアクションを起こす時代です.
始まりは Satoshi Nakamoto が発表した論文*とそれをベースに開発・プログラムされたビットコインで,これによりブロックチェーンが誕生しました.
ブロックチェーンは原則オープンアクセスなので誰でも参加できますし,参加するための承認を得る必要もありません.
さらに,取引履歴は全て公開されているので,仮に不正取引が行われても,それを追跡することが可能です!
*NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. 2008.
キーワードは「所有」

web3のキーワードは「所有」です!
- インターネット上で形成された個人データ(閲覧履歴・SNSへの投稿・消費行動など)は誰のものなのか?
- GAFAを代表とする一部の企業・組織がそれを独占しても良いのだろうか?
- 中央集権化が進行し続ける現状をただ受け入れるのではなく,そこから脱却して,知らぬ間に提供されている個人データの「所有」を取り戻そう!
このような思想・意思がweb3を築いている人々の間で共有されています.
そして,ブロックチェーンを活用すれば,理論上はそれが実現できます!
分散型科学(DeSci)の定義を知る

分散型科学(DeSci)を学ぶために必要な基本事項の整理が終わりました!

すでにすごい情報量です…

でも,これからが本番ですよ~先ずは DeSci の定義を見ていきましょう!
DeSciの定義現代の科学(伝統的な科学)が抱える課題を,ブロックチェーンを活用して解決することを目指すムーブメント

これが定義です.シンプルでしょ!

うん…もっと小難しい言葉が並ぶのかと思いました…

「分散化」とか「ブロックチェーン」の概要を先に学んだからだと思うよ!

非中央集権化(分散化)の考え・仕組みを科学研究に応用したら,既存の課題を解決できるかもってことですよね!

ですね!分かってるじゃん♪

それでは最後に,現代科学(伝統的な科学)が抱える課題を整理して,今回は終わりにしよう!
伝統的な科学(TradSci)が抱える課題
DeSciに対する科学という意味で,現代科学を伝統的な科学(Traditional science [TradSci])と表記されることがあります.
当ブログでもそれに倣って “TradSci” という単語を使用していきますね!

TradSci が抱える課題は大きく5つに分けられます!
- 資金の調達と配分の問題
- オープンサイエンスが進展しない問題
- 無償の査読と不透明な査読
- 採算が合わない分野のネグレクト
- 人材育成とマネジメント
研究資金の調達と配分の問題
研究プロジェクトを走らせるために資金が必要ですが,研究者が得られる資金の獲得率は減少するばかりですね.

目先の利益・課題解決・生活の役に立つことに直結しない基礎研究は特にその傾向が強い!
加えて,研究試薬等の価格や学術誌の出版費用も上昇が,研究費を確保しにくい大学や国の研究者の研究継続をより一層困難な状況に追い込んでいます.
また,公的な研究費は「担当審査員の主観による選別」で配分されるので,その分配方法の客観性や透明性に疑問を持つ研究者も多いでしょう.
オープンサイエンスが進まない問題
研究者ではない一般市民が科学に参加できるようにしたり,実験内容や結果を公開して誰でもアクセスできるようにすることをオープンサイエンスと言いますね!
しかし,有料閲覧のために研究機関の関係者しか読めない状態にある学術論文はたくさんありますし,実験データ(Raw data)へのアクセスも容易ではありません.

特に企業の研究データは独占される傾向にあり,研究者間の交流や共同研究が起こりにくくなっています.
無償の査読と不透明な査読
ピアレビューによる査読活動は学術コミュニケーションの透明性を確保する上で重要です.
しかし,査読活動は無償のボランティア!

各研究者の自己犠牲的努力のお陰と言っても過言ではありません.
何かしらのインセンティブが無ければ,その自己犠牲を払う人は減り,研究の透明性を確保することが困難になるでしょう.
また,査読活動の記録は非公開である雑誌が多いので,そのプロセスに疑義が生じることもあります.
開発・販売の採算が合わない分野のネグレクト
患者数が少ないとか発生地域が貧困層で市場にならないという理由で研究開発が積極的に行われない分野が存在します.

例えば,私の専門の感染症分野では「顧みられない熱帯病」という言葉がありますね!
WHOが「⼈類が制圧しなければならない熱帯病」と指定する21種の疾患群で,約16億の人々がその感染リスクにさらされています.
しかし,その大半が主に熱帯の貧困地域なので,製薬会社は治療薬の研究開発を行いません.
人材育成とマネジメント
スポーツの世界では「名選手が必ずしも名監督にはならない」と言われていますが,研究業界でも同様でしょう.
研究者としては優秀だけれど,その人が指導者としても優秀かどうか別問題のはず!
でも,それを認識・理解できている人(教員)は少ないと感じています.
信頼関係という便利な言葉の下,「強要」と「支配」による指導を継続する昔ながらの教員・先輩はたくさんいるし,私もそういう環境で育ってきました.

私はそういう人にしか出会ったことがないし,新たにマネジメントを学ぶ意欲も無かったので,早々と研究者の道を断念したのですがwww
後進が知識と技術を研鑽できる「機会」と「環境」を用意する!
シンプルですが,これが指導者のやるべきことでしょう。
問題はそのやり方を誰も教えてくれない&うまく回る「仕組み」を共有できないことですね.
DeSciは何をするのか?
TradSciが抱える課題をまとめてきましたが,これを読んだ皆さんは「DeSciで具体的に何をするのか?」が気になったと思います.

細かい話は次回以降にしますが,すでにあるDeSciの使用例を簡単に紹介しますね!
- 分散型ネットワークを使用した研究資金の調達とその透明な分配
- 学術誌の分散型データベースを提供
- 実験データをトークン化して研究者間で共有
- 査読活動の記録作成と研究者の貢献&説明責任の明確化
- 特定の問題を解決するためサイエンスDAOの設立

これらの背景には非中央集権化(分散化)の考えがありますし,その実現にはブロックチェーンが不可欠です!
【まとめ】分散型科学(DeSci)を知る
今回は「分散型科学(DeSci)とは何なのか?」を知るために必要な単語の理解・考え方をまとめました.
web3の専門家からしたら「説明が甘い!」とか「正確じゃない!」ってお叱りを受けるかもしれませんが…

できるだけ噛み砕いて,分かりやすく説明することに重きを置いたので許してくださいw
DeSciは簡単に言えば,「科学(知識・技術)の民主化」です.
- 研究成果やその応用から得られた製品&サービスを特定組織・地域の人々が独占して良いのだろうか?
- 目先の利益を追求し,基礎研究の価値をおざなりしてイイの?
- 研究対象となる分野の選択は市場規模だけで判断するしか方法はないの?
- 実験データの共有やコラボレーションは理想論なの?
- そもそも研究に貢献した者への評価がおかしくない?
TradSciの「当たり前」にブロックチェーンで挑もうとする動きそのものがDeSciなのです!

既存の科学研究の在り方を大きく変えると期待できるってことは伝わったでしょうか?

DeSciは上手く機能するんですか?

それはこれからの話なので「やってみないと分からない」と答えるほかありません.ただ,世界的に注目を集めている動きですから,その動向に注目して損はないでしょう.
もっと勉強したい方へ

DeSciに関する日本語の文献を集めてみました!
・デサイロ(De-Silo)のDeSciに関する連載【第1回】
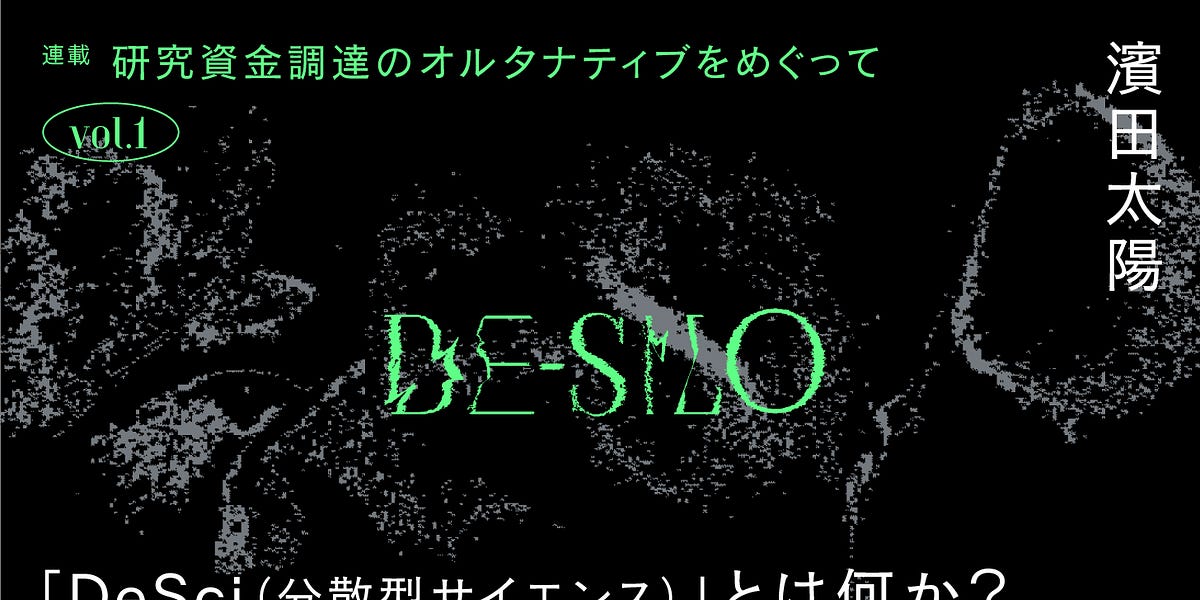
・デサイロ(De-Silo)のDeSciに関する連載【第2回】

・デサイロ(De-Silo)のDeSciに関する連載【第3回】
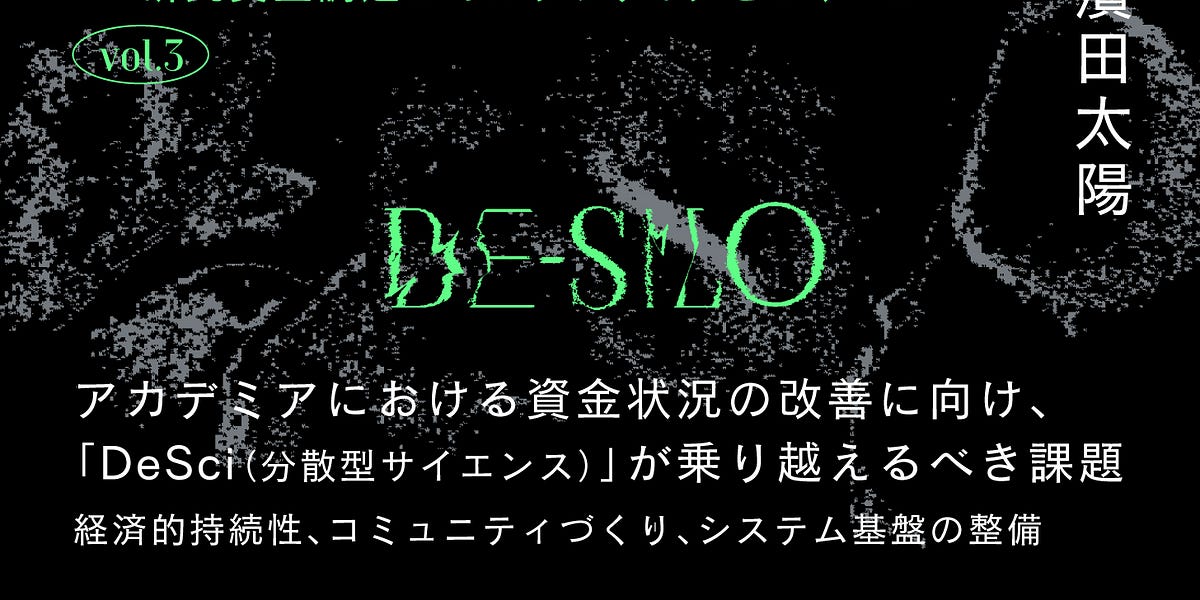
・デサイロ(De-Silo)のDeSciに関する連載【第4回】
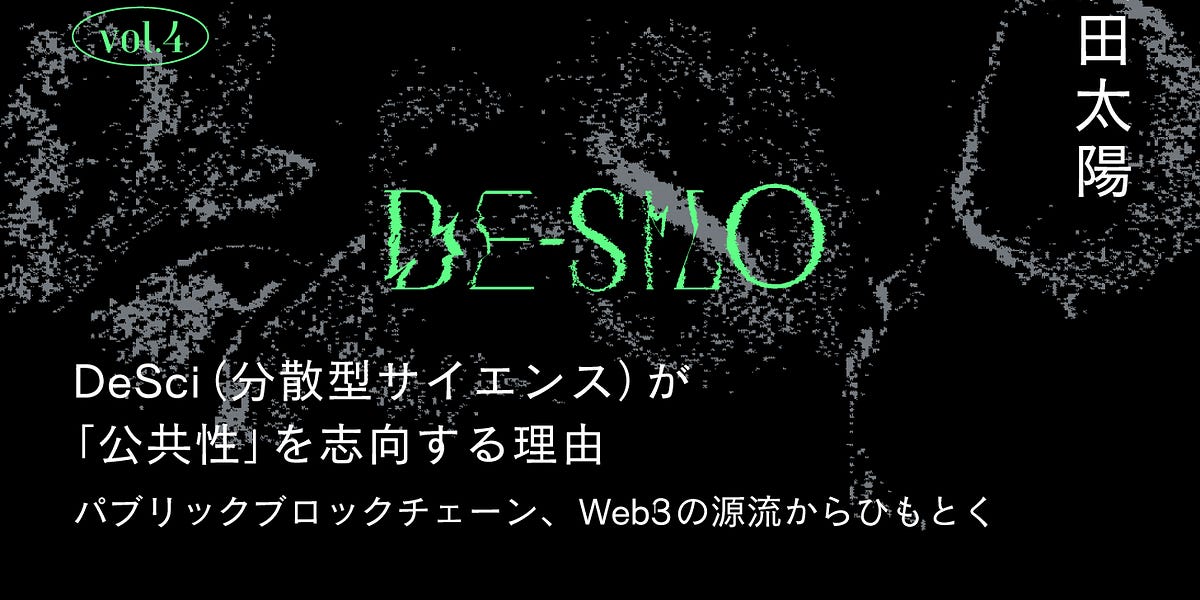
・デサイロ(De-Silo)のDeSciに関する連載【第5回】

・濱田太陽.Web3 社会がつなぐ研究と人と資金.アド・スタデ ィ ー ズ.2023a,vol.83.

・Forbes JAPANの記事

・BUSINESS INSIDERの記事
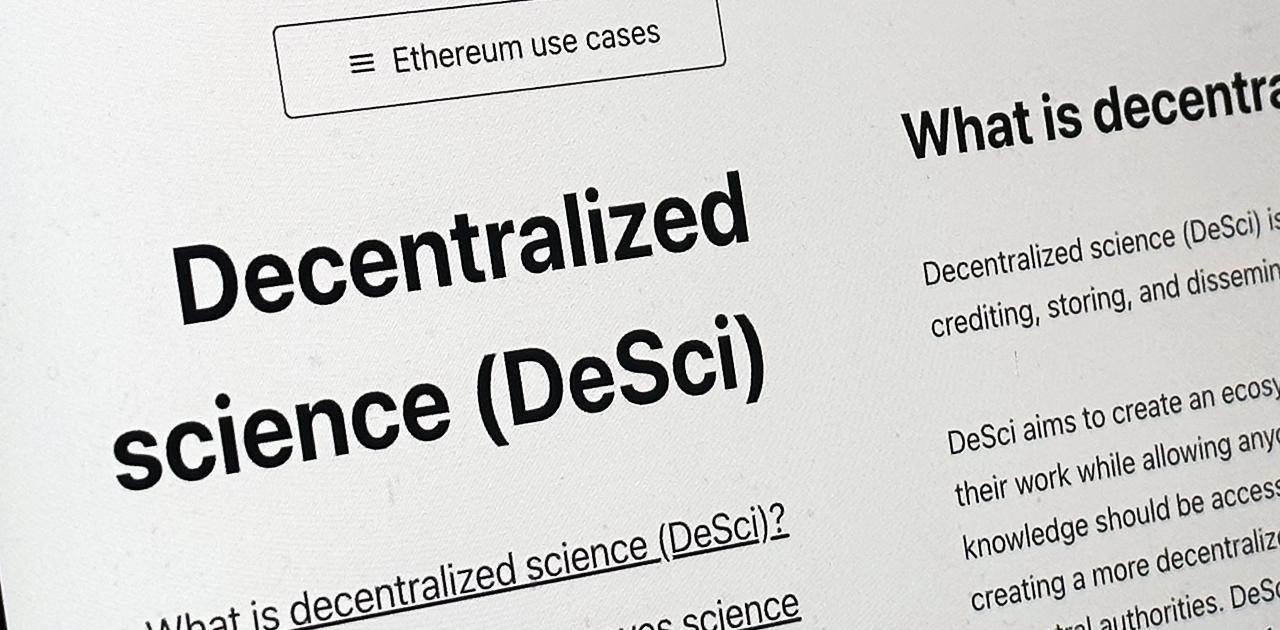
・濱田太陽. 分散型科学が拓く新たなエコシステム: DeSci. Tokyo が果たす役割. 情報の科学と技術, 2024, 74.3: 86-91.

これらの資料を読んで「分からない単語が多すぎる…」と思った方は以下の書籍が辞典代わりとなるのでオススメです!
・デジタルテクノロジー図鑑 「次の世界」をつくる

web3に関する情報収集がしたい方は読んで稼ぐアプリ*「ReadON」を使ってみましょう!
- アプリをダウンロード
- アカウント登録
- アプリの設定(招待コード[668BFA]の入力で 100 pt ゲット!)
- コンテンツを読む
*ReadONは無料で始めることができますが,アプリ内でトークン($READ)を稼ぐためにはねこNFT(にゃんこNFT)が必要です.ただし,$READはまだ上場していないので,ねこNFTを保有していても稼げません.

現在やることは次の3つ!
①ポイントを貯める(将来的には$READ,円,ドル,NFTなどに交換可能になる予定)
- ログインボーナスの獲得
- デイリークエストのクリア
- 読書の目標時間クリア
- 不定期で開催されるDiscordやLineでのポイント獲得イベント
②ポイントを消費して「ねこのパーツ」を集める
③経験値を獲得してReadON ArchiveのLv.を上げる

より詳しい説明はユーザーガイドおよびREVOX|ReadOnの公式Discordをご覧ください.
最後までお付き合いいただきありがとうございました.
次回もよろしくお願いいたします.
2024年4月20日 フール




コメント ~リクエストでも良いですよ~